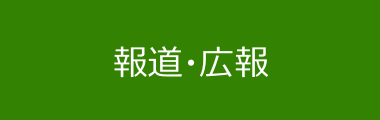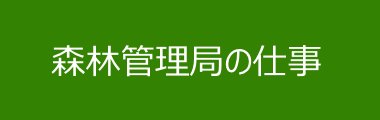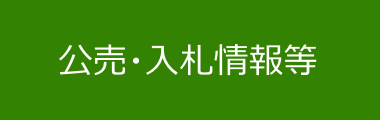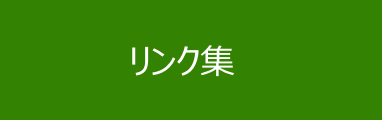植物・菌類
植物
エドヒガン
桜で有名な品種といえばソメイヨシノですが、エドヒガンはその親となります。特徴としては花が散った後に芽が出るという、萌芽のタイミングで、その特徴はしっかりとソメイヨシノに受け継がれています。
芽が花の邪魔をせず花の赤みが強いため、お花見にはうってつけです。
 |
 |
カスミザクラ
サクラ属の基本野生種の一つであり、ヤマザクラによく似た桜です。ヤマザクラのように葉と花が同時に展開しますが、ヤマザクラと違って新芽は新緑色(ヤマザクラは紅色)をしており、白い花と相まって上品な美しさがあります。
「楽しむための宴」としてのお花見の起源は平安時代といわれており、当時の桜はこのように葉と花が同時に展開する桜であったといいます。
鮮やかな白と緑のモザイクから、平安時代のお花見に思いをはせてみるのもよいかもしれません。
 |
コブシ
大きな白い花を枝先に咲かせるモクレン科の植物です。名前の由来はつぼみや果実の形が人の拳に似ていることからきています。
また、古くから農業の暦と深いかかわりがあり、花が咲く時期に田植えを行う地域もあったようです。
 |
ケケンポナシ
写真は果柄部分(果実を枝や茎につなぐ枝の部分)の物です。果柄部分は枝のような見た目に反して、果実はとても甘味が強く、ナシのような、カキのような味がします。
しかしながら、後味は少々渋みがあり、美味しいのだけれど後味が…と言いたくなります。
本などを調べると、霜に当たったケケンポナシは渋みが取れて美味しいとの記述がありますが、温かい大阪では霜に当たったケケンポナシを味見することは出来ませんでした。
また、ケケンポナシの葉にはホタロシドという甘味を阻害する成分があり、ケケンポナシの葉を噛むと30分は甘味を感じないそうです。
 |
イロハモミジ
知らぬ人はいないと言っていいほど、紅葉で有名な植物です。秋になると美しく紅葉し、その特徴的な葉の形と相まって、古くより人々に愛されてきました。
 |
 |
 |
サザンカ
漢字で書くと「山茶花」となる「サザンカ」。元々は「ザンサカ」と呼ばれていたようですが、江戸時代の言葉遊びによって、文字の倒置が行われ、「サザンカ」と呼ばれるようになったといいます。
椿の花によく似ていますが、椿の花は花が根元からボトッと落ちるのに対し、サザンカは花びらが一枚ずつ散っていきます。
 |
 |
リュウキンカ
茎が直立し、金色の花を咲かせるので「立金花(リュウキンカ)」と呼ばれています。4月上旬に鮮やかでそれなりに大きい花を咲かせるので、よく目を引きます。
 |
ササユリ
葉が笹に似ていることからササユリと呼ばれています。華奢な茎とアンバランスなほど大きい花を咲かせるので、メリハリがあり、「美しい」という言葉がよく似合います。
 |
 |
ヒガンバナ
秋の彼岸の頃に花を咲かせるのでヒガンバナと呼ばれている植物です。ヒガンバナというとお墓の周りなどに咲いているイメージがあり、怖い印象をもつ方もいるかもしれません。
というのもヒガンバナには根っこに毒があり、動物よけになることから、動物に掘り起こされたくないお墓や、田んぼのあぜなどに植えられることが多かったようです。
 |
フユイチゴ
冬に大粒の赤いラズベリーのような実をつけます。キイチゴの仲間では珍しく冬に実をつける為、クリスマスチェリーという名で苗が売られていることも。
美味しそうな見た目をしていますが、甘みがほぼ無くちょっと酸っぱくて種が大きく、味の薄いラズベリー感が否めないです。
ですが、食感はみずみずしく素敵な見た目をしているので、ついつい口に入れてしまいます。一つ見つけると大量に見つかることが多いため、それもまた食欲をそそります。
味の癖は少ない為、砂糖を多めに使って、ジャムを作ると美味しそうです。

センブリ
日本の民間薬として知られているセンブリは、秋ごろにその花を見ることができます。漢字では当薬と書き、その効能から「当(まさ)に薬(くすり)である」と言われていたことが由来のようです。
一般的にはセンブリ茶などが有名ですが、その味は非常に苦く、「良薬は口に苦し」という言葉がしっくりとくる植物と言えるでしょう。
 |
 |
菌類
ベニヒガサ
 |
 |
ハナオチバタケ
 |
テングタケ
 |
タマゴタケ
 |
 |
お問合せ先
箕面森林ふれあい推進センター
ダイヤルイン:075-414-9049