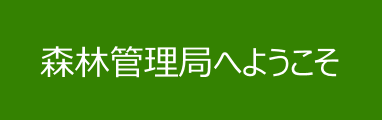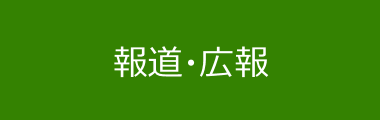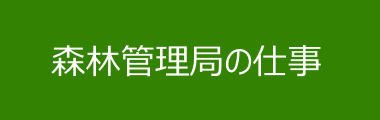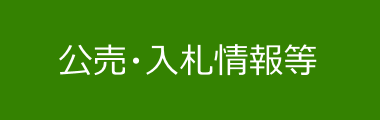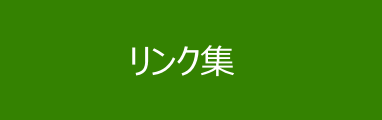(群集12)富士山生物群集保護林
1.森林管理署
静岡森林管理署2.森林計画区
富士森林計画区3.所在地
静岡県裾野市・富士宮市・富士市4.林小班
470は外5.面積
1027.09ha(保存地区:1027.09ha 保全利用地区:ha)6.設定年月日
平成3年4月1日(1991年4月1日)平成30年4月1日に旧浅木塚ヒノキ群落林木遺伝資源保存林(ヒノキ、464い、470は)、旧富士山大沢カラマツ・イラモミ・ウラジロモミ群落林木遺伝資源保存林(カラマツ、イラモミ、ウラジロモミ、46い,ろ、47い、48い、49い,ろ、52い,ろ,は、53い)、旧富士山東臼塚低山帯植物群落保護林、旧富士山亜高山帯植物群落保護林を統合した。7.法的規制
水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林、国立公園特別保護地区、国立公 園第1種特別地域、国立公園第2種特別地域、国立公園第3種特別地域 国立公園普通地域、鳥獣保護区、文化財保護法に基づく特別史跡名勝天然記念物。8.設定目的
富士山の山腹には、日本の低山帯から高山帯にわたる植生の垂直分布が模式的に存在し、太平洋気候区の典型的な森林として維持されている。低山帯には、ブナ、ミズナラ、カエデ類等の落葉広葉樹を主体とした天然林が成立し、亜高山帯には、カラマツ、イラモミ、 ウラジロモミ、コメツガ、シラビソなどを主体とした天然林が成立している。
また、丸尾と呼ばれる溶岩流上には、ヒノキ純林の特徴的な群落が形成され、スコリアの堆積地には、火山荒原草本群落が形成されている。
このため、当該地域の代表的なこれらの群落を主体とする地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術 の研究等に資するため設定する。
9.特 徴
標高1,380~2,790m。大沢崩れの左岸にある、標高1,500~2,800mに位置する保護林の西側の区域には、カラマツ・イラモミ・ウラジロモミなどからなる原生林が広がっている。
カラマツ林は、大沢を中心とする西向き斜面に最も大径木が多く生育し、人為の影響が一番及ばない原生的自然環境にある。
他にタカネノガリヤス-ダケカンバ群集、シラビソ-オオシラビソ群集が分布する。
富士山の南側、標高1,500m~2,300mに位置する保護林の中央部の区域には、カラマツ群落、タカネノガリヤス-ダケカンバ群集、シラビソ-オオシラビソ群集の亜高山性針葉樹林が分布している。
富士山原始林と呼ばれる亜高山性の自然植生は、この火山の南北両斜面にも発達するが、大沢を中心とする西向き斜面が最も大径木が多く、人為の影響が及んでいない原生的自然環境を維持している。
標高1,600m付近ではウラジロモミが優占し、コメツガ等の針葉樹が混生している。
亜高木層~低木層は広葉樹も混じり、草本層はスズタケが 繁茂している。
標高2,200m付近ではシラビソが優占し、ダケカンバやナナカマドが混じており、一部では、台風の影響と思われる倒木が多く見られる。
標高2,300m付近はスコリア土壌で、裸地面積が大きく植物の生育量は少ない。
オンタデやタイツリオウギ等の草本層が生育し、場所によっては樹高2m程度のミヤマハンノキが群生している。
標高2,660m付近ではカラマツ群落が見られ、多雪の影響や風衝地であるため、幹が湾曲している。
10.保護・管理及び利用に関する事項
保存地区の森林は、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねるものとする。保全利用地区の森林は、原則として、保存地区の森林に外部の環境の変化が直接及ばないよう緩衝の役割を果たすものとする。
11.保護林モニタリング概要
2024調査概要(PDF : 426KB)12.位置図
富士山生物群集保護地域(PDF : 397KB)お問合せ先
計画保全部 計画課
担当者:生態系保全係
ダイヤルイン:027-210-1265